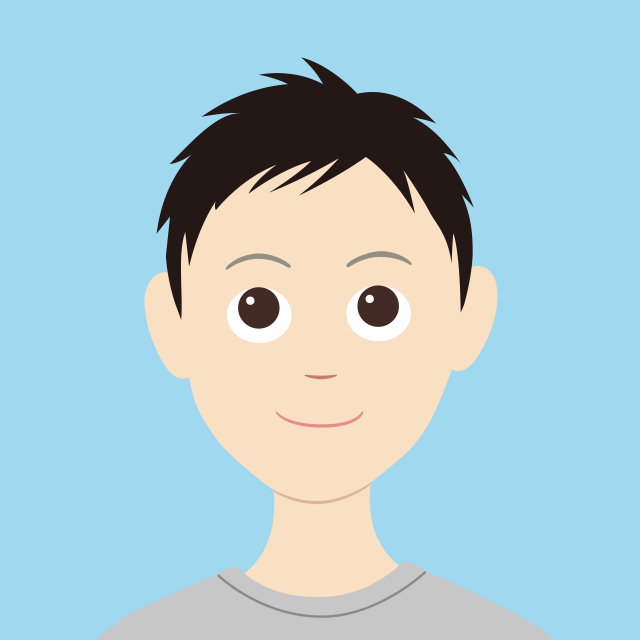毎年7月、南フランスの古都アヴィニョンは、街全体が巨大な舞台へと変貌します。世界中からアーティストと観客が集う、世界最大級の演劇の祭典「アヴィニョン演劇祭」です。
しかし、この華やかな祭典が、第二次世界大戦後の荒廃の中から、たった一人の男の情熱によって始まったことをご存知でしょうか?
この記事では、アヴィニョン演劇祭が1947年に誕生した経緯から、公式プログラム「イン」と自由参加の「オフ」という二つの顔を持つに至った歴史、数々の危機を乗り越え、現代の環境問題や多様性へと取り組む現在までの道のりを、誰にでも分かりやすく徹底解説します。
演劇祭の魅力と、それがなぜ「必要なるユートピア(理想郷)」と呼ばれるのか、その秘密に迫りましょう。
目次
1. 創設期(1947-1971年):ジャン・ヴィラールの夢と「人民演劇」の誕生
アヴィニョン演劇祭の物語は、創設者ジャン・ヴィラールの夢から始まります。それは、一部のエリート層だけが楽しむパリ中心の演劇から脱却し、誰もが楽しめる「人民演劇」を創り出すという、壮大な挑戦でした。
戦後の混乱から生まれた演劇の祭典
1947年、俳優であり演出家であったジャン・ヴィラールは、アヴィニョン法王庁の荘厳な中庭で演劇を上演してほしいと依頼されます。当初、彼はこの巨大すぎる空間に戸惑い、一度は断りました。
しかし、彼は逆にある大胆な提案をします。当時ほとんど無名だった作品を含む3本を上演するというものでした。これが、挑戦的な作品を積極的に紹介するという、アヴィニョン演劇祭の原点となります。
ヴィラールの核心的な理念は「人民演劇(théâtre populaire)」でした。これは、演劇を一部の特権階級のものではなく、若者をはじめとする**広く民衆に開かれた「公共サービス」**と捉える考え方です。彼は、文化をパリから地方へ、特権階級から民衆へと解放しようとしたのです。
この情熱に、ジェラール・フィリップやジャンヌ・モローといった若きスター俳優たちが共鳴。彼らの参加は、アヴィニョンをフランス演劇の最前線へと一気に押し上げました。
国立民衆劇場(TNP)との連携と拡大
1951年、ヴィラールがパリの国立民衆劇場(Théâtre National Populaire, TNP)のトップに就任すると、演劇祭はTNPの夏の拠点として機能し、その公共的な性格をさらに強めます。
1966年以降は、モーリス・ベジャールのダンスやゴダールの映画を上映するなど、演劇以外の分野にも門戸を開き、総合的な芸術祭へと発展していきました。
2. 「イン」と「オフ」:二つの顔が創り出す「劇場都市」アヴィニョン
アヴィニョン演劇祭を語る上で欠かせないのが、公式プログラム「イン(In)」と、同時期に自然発生的に生まれたフリンジ部門「オフ(Off)」の存在です。
この二つの存在が、アヴィニョンを世界で唯一無二の「劇場都市」にしています。
カウンターカルチャーから生まれた「オフ」
1966年、演出家アンドレ・ベネデットが、公式プログラムとは無関係に自主的な上演を行いました。これが「オフ」の始まりです。
かつては革命的だったヴィラールの「イン」が、時を経て権威的になったと感じたアーティストたちが、「もっと自由に、自分たちの作品を上演したい」という欲求から始めた運動でした。
当初は「イン」と「オフ」の間には緊張関係もありましたが、やがて両者は対立しながらも互いに不可欠な関係へと変化していきます。
一目でわかる!「イン」と「オフ」の違い
| 特徴 | フェスティバル・イン(公式) | フェスティバル・オフ(非公式) |
| 始まり | 1947年、ジャン・ヴィラールによる | 1966年、アンドレ・ベネデットによる |
| 運営 | 国や市からの助成金で運営される非営利団体 | 劇団が主体となる非営利団体(AF&C) |
| 作品の選び方 | 芸術監督が厳選した約45作品 | 誰でも自由に参加可能。1000以上の団体が参加 |
| 理念 | 芸術的卓越性、国際的創造 | 自発性、独立性、表現の自由 |
| 主な会場 | 法王庁中庭、歴史的建造物、専用劇場 | 小劇場、学校、路上などあらゆる場所 |
「イン」が提供する世界最高峰の芸術に、「オフ」の爆発的なエネルギーと混沌が加わる。この二つの化学反応こそが、7月のアヴィニョンを街中が劇場になる魔法のような空間に変えているのです。
今や「オフ」はフランス最大の舞台芸術マーケットとなり、数千人のプロデューサーやジャーナリストが未来のスターを探しに集まります。
3. 試練の時代:五月革命とストライキが演劇祭を変えた
順風満帆に見えた演劇祭の歴史ですが、そのアイデンティティを揺るがす大きな危機が二度訪れます。これらの出来事は、結果的に演劇祭をより強く、成熟させるきっかけとなりました。
1968年「五月革命」の衝撃:創設者ヴィラールへの批判
1968年5月、フランス全土を巻き込んだ学生と労働者の反乱運動「五月革命」は、演劇祭にも波及しました。かつて革命の旗手だった創設者ヴィラールは、新しい世代の若者たちから「古い体制の象徴」「パパの文化」と激しい批判の的になります。
演劇祭は「文化のスーパーマーケット」と揶揄され、大きな混乱に見舞われました。この経験はヴィラールに深い衝撃を与え、彼は3年後にこの世を去りました。
2003年、史上初の中止:芸術家のストライキ
2003年、演劇祭は史上初の中止に追い込まれます。原因は、「アンテルミッタン」と呼ばれる舞台芸術家のための失業保険制度改革に抗議する大規模なストライキでした。
この危機は、フランスの文化政策の根幹を揺るがす大論争に発展。「芸術は神聖なもので、止めるべきではない」と主張する大御所演出家と、「生活がかかっている」と訴える現場のアーティストたちの間で、深い溝が浮き彫りになりました。
これら二つの危機は、演劇祭を支える「偉大な芸術家」と、現場で働く多くの「文化労働者」との間の意識のズレが表面化した事件でした。この経験を経て、演劇祭はより専門的で、政治的に中立な運営体制へと移行していくことになります。
4. ヴィラール後のアヴィニョン:国際化と歴代監督たちの挑戦
ヴィラールの死後、演劇祭は歴代の芸術監督たちの手によって、その姿を変化させながら発展していきます。特に大きな流れは「国際化」でした。
ケーススタディ:ピーター・ブルックの『マハーバーラタ』(1985年)
1985年に上演された、イギリスの巨匠ピーター・ブルックによる9時間の大作『マハーバーラタ』は、演劇史に残る伝説的な事件となりました。
インドの古代叙事詩を、16カ国の多国籍キャストで舞台化したこの作品は、アヴィニョンが真に国際的な芸術祭へと飛躍する象徴となります。
しかし同時に、この作品は「西洋の視点で異文化を都合よく解釈しているのではないか」という文化盗用をめぐる大きな論争も巻き起こしました。
この論争は、異なる文化が交差する現代において、芸術がどうあるべきかを世界に問いかける重要なきっかけとなりました。
現代の監督たちへ受け継がれるバトン
その後も、一人の「アソシエイト・アーティスト」を共同キュレーターとして招くモデルや、自身も演出家である「芸術家=監督」モデルへの回帰など、演劇祭は常にそのあり方を問い直してきました。
2023年に就任した現在の芸術監督ティアゴ・ロドリゲスは、演劇を「市民の祝祭」と捉え、アーティストと観客が出会う民主的な空間としての役割を重視しています。
5. 現代のアヴィニョン:未来へつなぐための取り組み
今日のアヴィニョン演劇祭は、単なる舞台芸術の祭典にとどまりません。歴史を未来につなぎ、現代社会の課題に応える多面的な文化機関として進化し続けています。
未来を創る拠点「La FabricA」
2013年に完成した「La FabricA」は、演劇祭の通年の創作・リハーサル施設です。特筆すべきは、その舞台が法王庁の中庭の舞台と全く同じ寸法で設計されていること。これにより、アーティストは最高の環境で作品作りに専念できます。
さらに、この施設は年間を通じて地域住民のためのワークショップや芸術教育の拠点としても機能しており、演劇祭が7月だけのイベントではなく、地域に根ざした文化の拠点へと変貌を遂げたことを象徴しています。
環境問題、多様性への取り組み
現代の演劇祭は、創設者ヴィラールの「公共サービス」の精神を、21世紀の形で再解釈しています。
- 環境への配慮: 公共交通の利用促進、廃棄物の削減、省エネなど、環境負荷を低減する具体的な取り組みを推進。
- 多様性と包摂: プログラムにおける男女均等の保証、ハラスメント防止、障害を持つ人々のためのアクセシビリティ確保などを徹底。
- 新たな観客の開拓: 初めて演劇を観る人々を対象としたプロジェクトなどを通じて、文化体験の敷居を下げています。
これらの取り組みは、ヴィラールの遺産を未来へとつなぎ、演劇祭が現代社会において意義ある存在であり続けるための、重要な挑戦なのです。
結論:「必要なるユートピア」の物語は続く
アヴィニョン演劇祭の歴史は、創設者ジャン・ヴィラールの理想と、芸術、政治、社会の複雑な現実との間で繰り広げられてきた、絶え間ない対話の物語です。
「イン」と「オフ」の対立と共存、革命やストライキによる危機、そして絶え間ない自己変革。その歴史は決して平坦なものではありませんでした。
アヴィニョン演劇祭が今日まで輝きを失わないのは、それが完成された理想郷だからではありません。
むしろ、プロヴァンスの夏の光の下、「芸術とは何か」「社会におけるその役割とは何か」という根源的な問いが、毎年新たに生まれ、議論される「必要なるユートピア」**であり続けているからです。
その物語は、これからも世界中のアーティストと観客を巻き込みながら、続いていくのです。